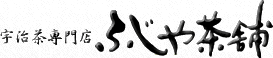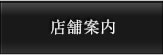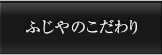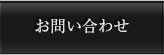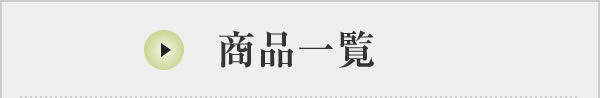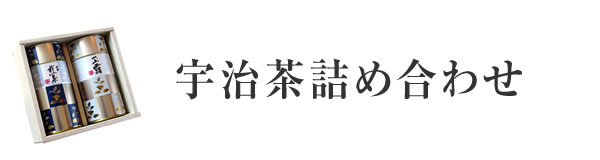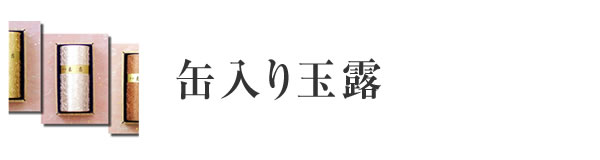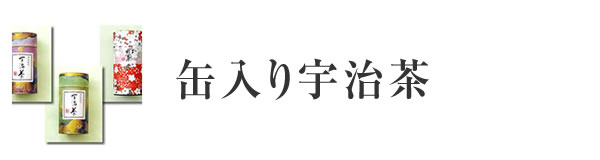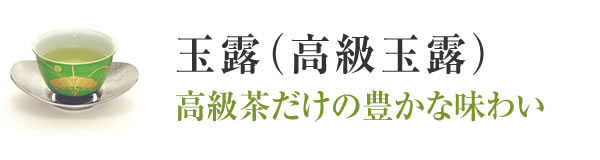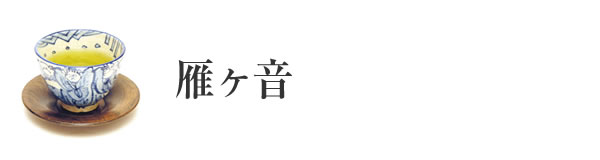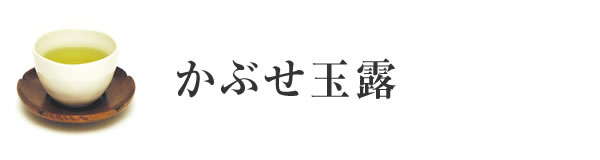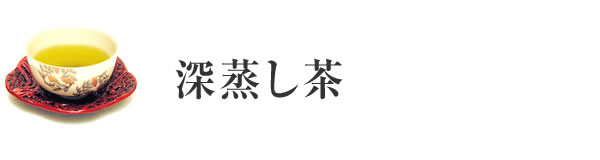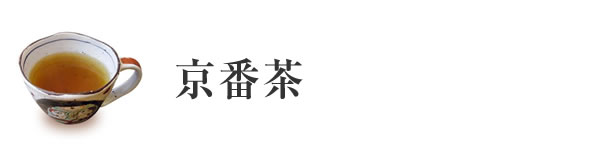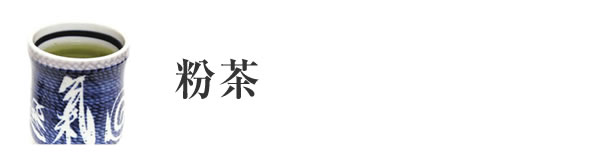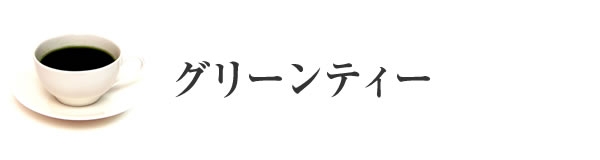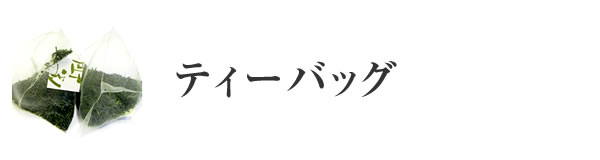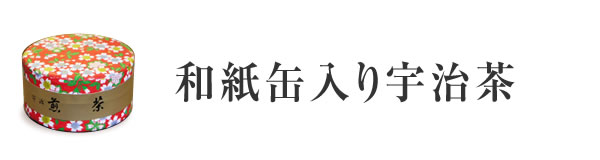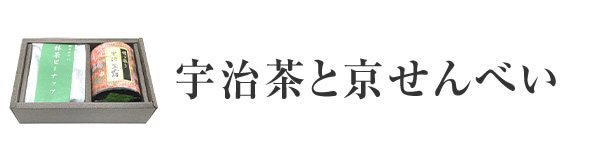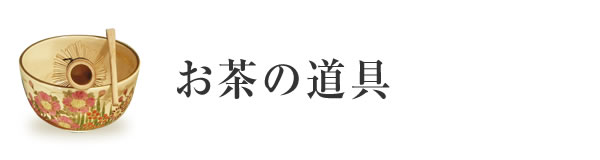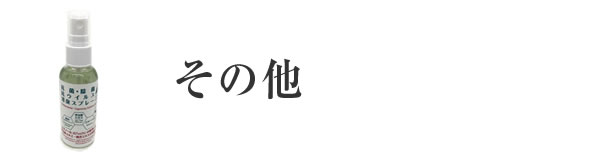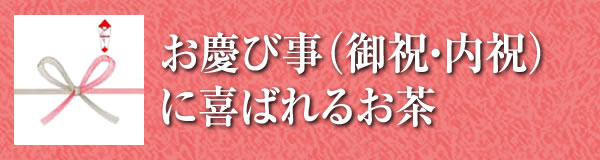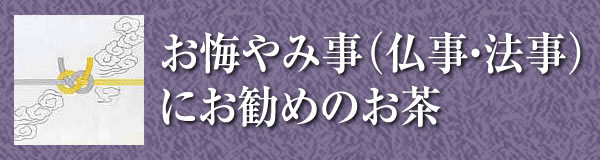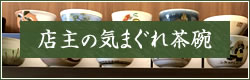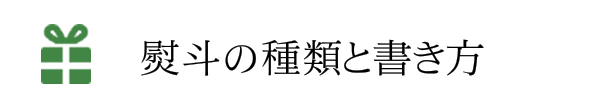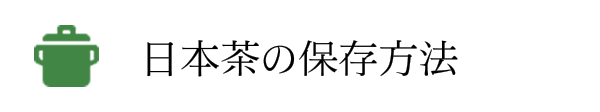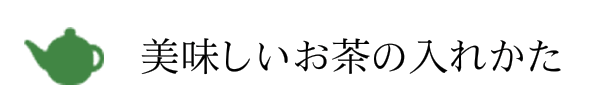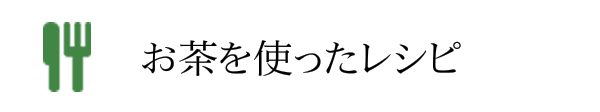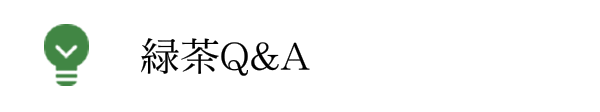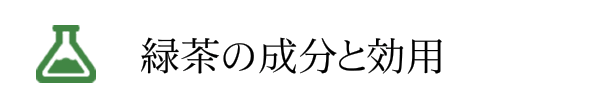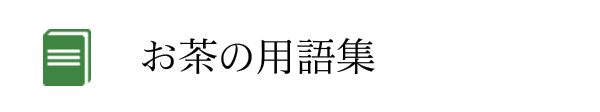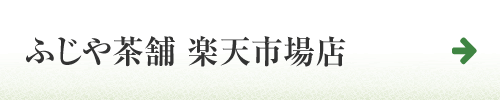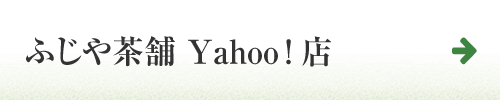- 2025-09-26 (金) 6:00
- お役立ちコラム
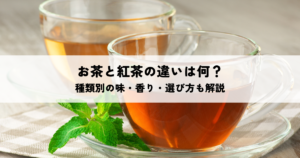
お茶の豊かな世界へようこそ。
毎日飲むお茶ですが、その種類や違いについて、改めて考えてみたことはありますか?
緑茶、紅茶、烏龍茶…どれも「お茶」ですが、色も香りも味も大きく違いますよね。
実は、これらの違いは、茶葉の処理方法、特に「発酵」という工程に大きく関わっているのです。
今回は、お茶の種類の違いを、発酵度合いと茶葉の種類という視点から見ていきましょう。
お茶選びのヒントになれば幸いです。
お茶の種類の違い
茶葉の発酵度合いの違い
お茶の種類は、茶葉の発酵度合いによって大きく分類されます。
発酵とは、茶葉に含まれる成分が酸化することです。
りんごの皮をむいて放置すると茶色く変色しますが、あれと同じ現象です。
発酵の度合いによって、お茶の色、香り、そして味も大きく変化します。
緑茶は発酵させない「不発酵茶」、紅茶は完全に発酵させる「完全発酵茶」、烏龍茶は途中で発酵を止める「半発酵茶」です。
他にも、発酵度合いによって黄茶、白茶、黒茶などがあります。
茶葉の種類による違い
お茶の原料となるのは、全て「チャノキ(カメリア・シネンシス)」という植物です。
しかし、チャノキにも様々な種類があり、その違いもお茶の味や香りに影響を与えます。
例えば、日本で多く栽培されているのは「中国種」で、葉が小さく、苦味成分であるタンニン(カテキン類)が少ないため、緑茶に適しています。
一方、「アッサム種」は葉が大きく、タンニンが多いので、紅茶の原料として使われます。
同じチャノキでも、品種によってお茶の性質は大きく異なるのです。
味と香りの違い
発酵度合いと茶葉の種類によって、お茶の味と香りは大きく異なります。
緑茶は、鮮やかな緑色と爽やかな香りが特徴です。
渋みや苦みも感じますが、種類によってその強さは異なります。
紅茶は、赤褐色で、濃厚な香り、そして甘みとコクが特徴です。
烏龍茶は、緑茶と紅茶の中間的な性質を持ち、様々な風味があります。
半発酵茶であるため、発酵度合いによって、緑茶に似たものから紅茶に近いものまで、幅広いバリエーションを楽しめます。
お茶の選び方
お茶を選ぶ際には、まず自分の好みに合った発酵度合いを考えることが重要です。
さっぱりとした味が好みなら緑茶、濃厚な味が好みなら紅茶、そしてその中間が好みなら烏龍茶を選ぶと良いでしょう。
また、茶葉の種類も考慮すると、より深いお茶の世界を楽しむことができます。
様々な種類のお茶を試飲し、好みを見つけることが、お茶選びの第一歩です。
季節や気分に合わせて、お茶を選ぶのも楽しみ方のひとつです。

紅茶の種類と特徴
紅茶の発酵工程
紅茶は、茶葉を完全に発酵させることで作られます。
その工程は、まず茶葉を萎凋(いちょう)させて水分を減らし、次に揉捻(じゅうねん)して茶葉の細胞を壊し、発酵を促進します。
その後、発酵室で適切な温度と湿度で発酵させ、最後に乾燥することで、紅茶独特の風味と色合いが生まれます。
発酵の時間は、紅茶の種類によって異なります。
紅茶の種類による風味の違い
紅茶は、世界各地で生産されており、産地や品種によって、風味に大きな違いがあります。
例えば、インドのアッサムは、力強いコクと香りが特徴です。
一方、スリランカのウバは、すっきりとした爽やかさが魅力です。
ダージリンは、繊細で華やかな香りが人気です。
これらの違いは、土壌、気候、栽培方法など様々な要因が複雑に絡み合って生み出されています。
紅茶の淹れ方と楽しみ方
紅茶の淹れ方は、使用する紅茶の種類や好みによります。
一般的には、熱湯を注ぎ、数分間蒸らして、茶葉から成分を抽出します。
ミルクや砂糖を加えて飲むのも、紅茶の楽しみ方の一つです。
ストレートで飲むのも良いですし、レモンを加えて爽やかに楽しむのもおすすめです。
紅茶の種類によって、最適な淹れ方や楽しみ方が異なるので、ぜひ色々な方法を試して、最高の紅茶を見つけてみてください。

まとめ
今回は、お茶の種類、特に緑茶と紅茶の違いについて解説しました。
どちらも同じチャノキの葉から作られていますが、発酵の度合いによって、色、香り、味に大きな違いが生じることが分かりました。
紅茶の発酵工程や、様々な紅茶の風味の違いについても触れました。
お茶の種類は豊富で、それぞれに魅力があります。
この記事が、お茶選びの参考になれば幸いです。
ぜひ、色々な種類のお茶を味わって、お気に入りを見つけてみてください。