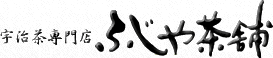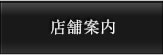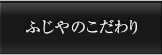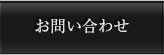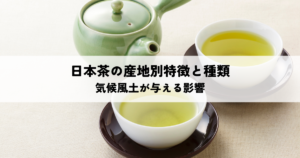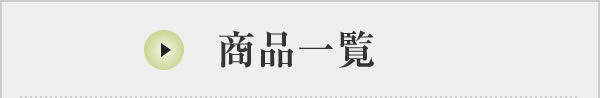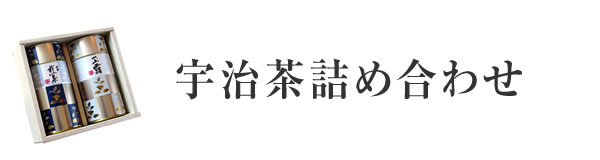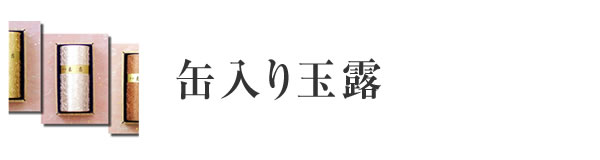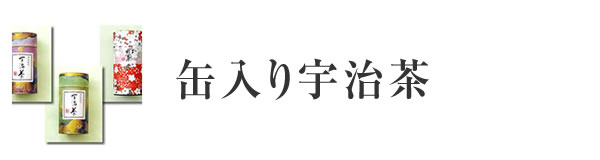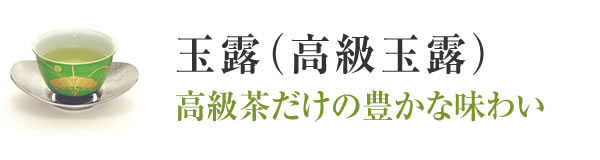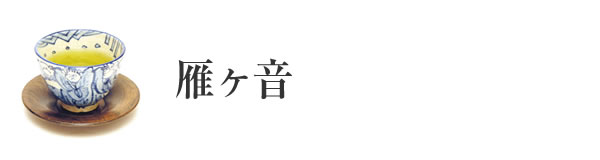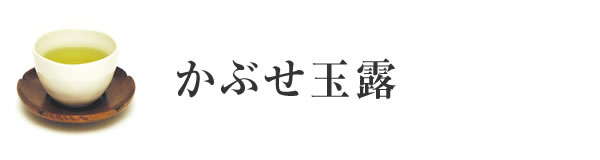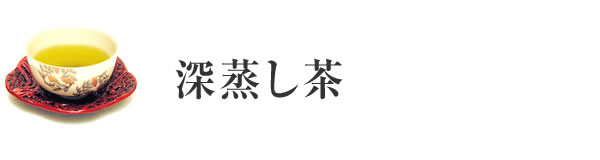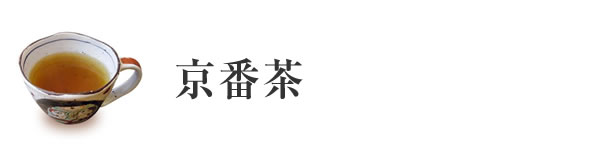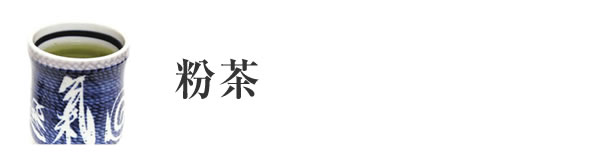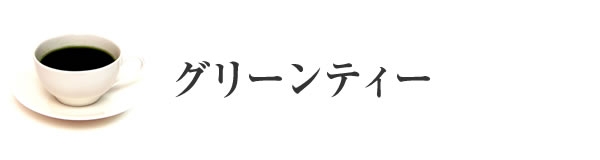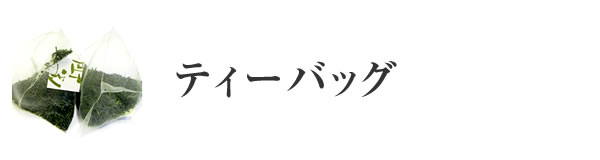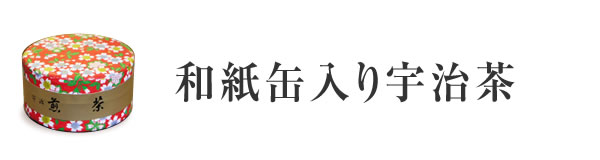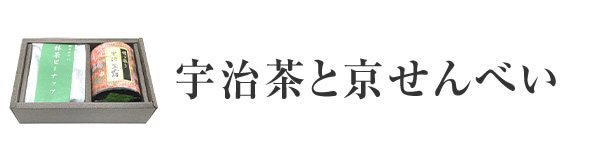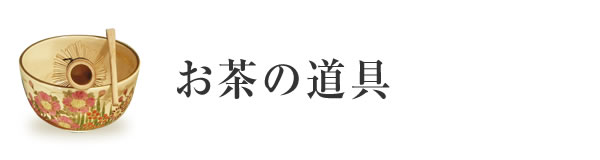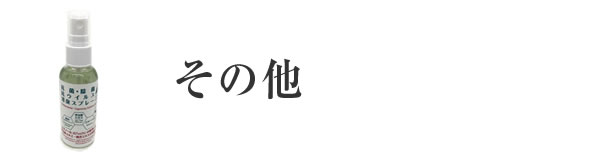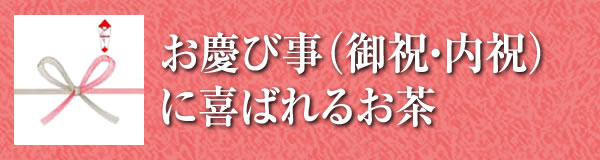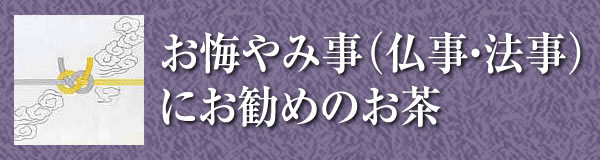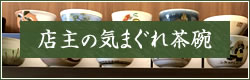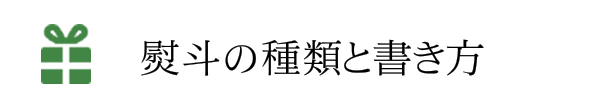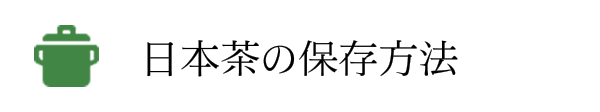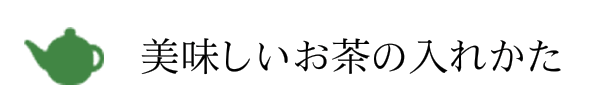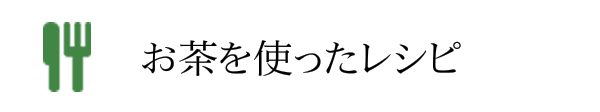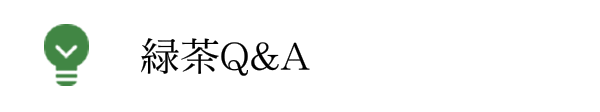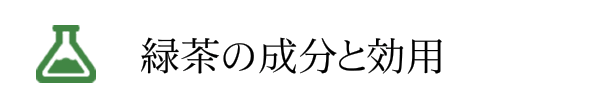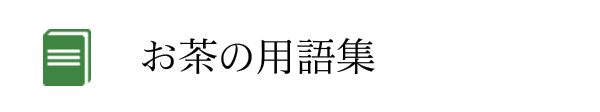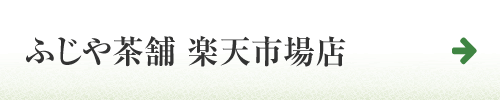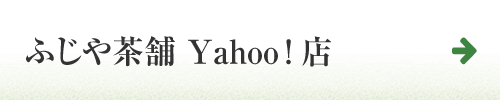2025-09
日本茶の産地別特徴と種類を解説!気候風土が与える影響とは?
- 2025-09-30 (火)
- お役立ちコラム
日本茶の主な産地
静岡県
鹿児島県
京都府
福岡県
各産地の気候風土の特徴は?
静岡県
鹿児島県
京都府
福岡県
産地によって日本茶の種類は異なる?
静岡県
鹿児島県
京都府
福岡県
まとめ
お茶の名前一覧!日本茶・紅茶・中国茶を種類別に解説
- 2025-09-28 (日)
- お役立ちコラム
日本茶の種類
煎茶とは日本茶の代表格
玉露とは旨味が凝縮された高級茶
抹茶とは茶葉を粉末にしたお茶
ほうじ茶とは香ばしい焙煎茶
紅茶の種類は?
ダージリンとは繊細な味わいの紅茶
アッサムとはコクのある力強い紅茶
アールグレイとはベルガモットで香りづけした紅茶
セイロンとはスリランカ産の紅茶
ハーブティーの種類は?
カモミールとはリラックス効果のあるハーブティー
ペパーミントとは爽快感のあるハーブティー
ローズマリーとは記憶力向上に効果があるハーブティー
レモングラスとはレモンのような香りのハーブティー
中国茶の種類は?
烏龍茶とは半発酵茶
プーアル茶とは黒茶の一種
ジャスミン茶とはジャスミンの花で香りづけしたお茶
お茶の名前一覧を確認できるサイト
日本茶インストラクター協会のサイト
紅茶専門店サイト
ハーブティー専門店サイト
まとめ
煎茶に含まれるビタミンEの秘密とは?健康効果を高める方法
- 2025-09-27 (土)
- お役立ちコラム
 は古くから愛飲され、その豊かな風味と健康への効果が注目されています。
は古くから愛飲され、その豊かな風味と健康への効果が注目されています。
近年では、お茶に含まれる成分の中でも、抗酸化作用を持つビタミンEへの関心が高まっています。
しかし、煎茶から効率的にビタミンEを摂取するにはどうすれば良いのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、煎茶のビタミンE含有量や、効率的な摂取方法について、具体的なデータや方法を交えながらご紹介します。
煎茶のビタミンE含有量
煎茶の種類による違い
煎茶の種類によって、ビタミンEの含有量は異なります。
一般的に、茶葉の品質や生育環境、製造方法によって含有量が変化します。
高級煎茶ほど、ビタミンEの含有量が多い傾向があります。
また、新茶は古茶に比べてビタミンEを多く含むことが知られています。
ビタミンEの吸収率を高める方法
ビタミンEは脂溶性ビタミンであるため、油と一緒に摂取することで吸収率を高めることができます。
例えば、煎茶を使った料理に、ゴマ油やオリーブオイルなどを加えることで、より効率的にビタミンEを摂取できます。
また、ビタミンEは熱に比較的強いので、煎茶を煮出して飲む方法も有効です。
1日の摂取目安量
厚生労働省が示す1日のビタミンEの摂取目安量は、成人男性で6.5mg、成人女性で6.0mgです。
煎茶1杯あたりのビタミンE含有量は、茶葉の種類や淹れ方によって大きく変動しますが、目安として1日に数杯の煎茶を摂取することで、十分な量のビタミンEを摂取できる可能性があります。

ビタミンEを効率的に摂取する方法
煎茶の適切な淹れ方
ビタミンEは水に溶けにくい性質を持つため、煎茶を淹れる際には、熱湯を使用し、茶葉を十分に抽出することが重要です。
抽出時間を長くすることで、より多くのビタミンEを抽出できます。
ただし、抽出時間が長すぎると、苦味や渋みが強くなる可能性があるため、適度な時間を見つけることが大切です。
茶葉の選び方と保存方法
ビタミンEを多く含む煎茶を選ぶためには、茶葉の品質に注目しましょう。
新茶や高級煎茶は、ビタミンEの含有量が多い傾向があります。
また、茶葉は直射日光や高温多湿を避けて保存することが重要です。
適切な保存方法によって、ビタミンEの劣化を防ぎ、より長く栄養価の高い煎茶を楽しむことができます。
煎茶を使ったレシピ提案
煎茶の茶葉をそのまま食べる「茶食」もおすすめです。
茶殻を使った料理や、粉末にした煎茶を料理や飲み物に混ぜ込む方法もあります。
例えば、茶殻をおひたしやふりかけに利用したり、粉末煎茶をパンケーキやクッキーの生地に混ぜ込むのも良いでしょう。
これらを通して、ビタミンEを効率的に摂取できます。

まとめ
煎茶には、抗酸化作用を持つビタミンEが豊富に含まれています。
ビタミンEの含有量は、煎茶の種類、淹れ方、保存方法によって影響を受けます。
熱湯でじっくりと抽出したり、油と一緒に摂取することで、吸収率を高めることができます。
また、茶葉をまるごと食べる「茶食」を取り入れることで、より効率的にビタミンEを摂取できます。
日々の生活に煎茶を取り入れ、健康的な生活を送りましょう。
お茶と紅茶の違いは何?種類別の味・香り・選び方も解説
- 2025-09-26 (金)
- お役立ちコラム
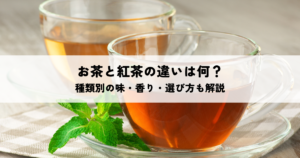
お茶の豊かな世界へようこそ。
毎日飲むお茶ですが、その種類や違いについて、改めて考えてみたことはありますか?
緑茶、紅茶、烏龍茶…どれも「お茶」ですが、色も香りも味も大きく違いますよね。
実は、これらの違いは、茶葉の処理方法、特に「発酵」という工程に大きく関わっているのです。
今回は、お茶の種類の違いを、発酵度合いと茶葉の種類という視点から見ていきましょう。
お茶選びのヒントになれば幸いです。
お茶の種類の違い
茶葉の発酵度合いの違い
お茶の種類は、茶葉の発酵度合いによって大きく分類されます。
発酵とは、茶葉に含まれる成分が酸化することです。
りんごの皮をむいて放置すると茶色く変色しますが、あれと同じ現象です。
発酵の度合いによって、お茶の色、香り、そして味も大きく変化します。
緑茶は発酵させない「不発酵茶」、紅茶は完全に発酵させる「完全発酵茶」、烏龍茶は途中で発酵を止める「半発酵茶」です。
他にも、発酵度合いによって黄茶、白茶、黒茶などがあります。
茶葉の種類による違い
お茶の原料となるのは、全て「チャノキ(カメリア・シネンシス)」という植物です。
しかし、チャノキにも様々な種類があり、その違いもお茶の味や香りに影響を与えます。
例えば、日本で多く栽培されているのは「中国種」で、葉が小さく、苦味成分であるタンニン(カテキン類)が少ないため、緑茶に適しています。
一方、「アッサム種」は葉が大きく、タンニンが多いので、紅茶の原料として使われます。
同じチャノキでも、品種によってお茶の性質は大きく異なるのです。
味と香りの違い
発酵度合いと茶葉の種類によって、お茶の味と香りは大きく異なります。
緑茶は、鮮やかな緑色と爽やかな香りが特徴です。
渋みや苦みも感じますが、種類によってその強さは異なります。
紅茶は、赤褐色で、濃厚な香り、そして甘みとコクが特徴です。
烏龍茶は、緑茶と紅茶の中間的な性質を持ち、様々な風味があります。
半発酵茶であるため、発酵度合いによって、緑茶に似たものから紅茶に近いものまで、幅広いバリエーションを楽しめます。
お茶の選び方
お茶を選ぶ際には、まず自分の好みに合った発酵度合いを考えることが重要です。
さっぱりとした味が好みなら緑茶、濃厚な味が好みなら紅茶、そしてその中間が好みなら烏龍茶を選ぶと良いでしょう。
また、茶葉の種類も考慮すると、より深いお茶の世界を楽しむことができます。
様々な種類のお茶を試飲し、好みを見つけることが、お茶選びの第一歩です。
季節や気分に合わせて、お茶を選ぶのも楽しみ方のひとつです。

紅茶の種類と特徴
紅茶の発酵工程
紅茶は、茶葉を完全に発酵させることで作られます。
その工程は、まず茶葉を萎凋(いちょう)させて水分を減らし、次に揉捻(じゅうねん)して茶葉の細胞を壊し、発酵を促進します。
その後、発酵室で適切な温度と湿度で発酵させ、最後に乾燥することで、紅茶独特の風味と色合いが生まれます。
発酵の時間は、紅茶の種類によって異なります。
紅茶の種類による風味の違い
紅茶は、世界各地で生産されており、産地や品種によって、風味に大きな違いがあります。
例えば、インドのアッサムは、力強いコクと香りが特徴です。
一方、スリランカのウバは、すっきりとした爽やかさが魅力です。
ダージリンは、繊細で華やかな香りが人気です。
これらの違いは、土壌、気候、栽培方法など様々な要因が複雑に絡み合って生み出されています。
紅茶の淹れ方と楽しみ方
紅茶の淹れ方は、使用する紅茶の種類や好みによります。
一般的には、熱湯を注ぎ、数分間蒸らして、茶葉から成分を抽出します。
ミルクや砂糖を加えて飲むのも、紅茶の楽しみ方の一つです。
ストレートで飲むのも良いですし、レモンを加えて爽やかに楽しむのもおすすめです。
紅茶の種類によって、最適な淹れ方や楽しみ方が異なるので、ぜひ色々な方法を試して、最高の紅茶を見つけてみてください。

まとめ
今回は、お茶の種類、特に緑茶と紅茶の違いについて解説しました。
どちらも同じチャノキの葉から作られていますが、発酵の度合いによって、色、香り、味に大きな違いが生じることが分かりました。
紅茶の発酵工程や、様々な紅茶の風味の違いについても触れました。
お茶の種類は豊富で、それぞれに魅力があります。
この記事が、お茶選びの参考になれば幸いです。
ぜひ、色々な種類のお茶を味わって、お気に入りを見つけてみてください。
オーガニックティーとは?健康と美容を叶える選び方
- 2025-09-25 (木)
- お役立ちコラム

毎日を健康的に過ごしたい方へ。
心と体のバランスを整え、活き活きとした日々を送るために、オーガニックティーは最適な選択肢と言えるでしょう。
自然の恵みと深い味わいを堪能できるだけでなく、健康にも良い影響を与えてくれる可能性を秘めているのです。
今回は、オーガニックティーの魅力を余すことなくお伝えします。
選び方から健康効果まで、オーガニックティーの世界を一緒に探求していきましょう。
オーガニックティーの選び方
有機JASマークの確認方法
オーガニックティーを選ぶ際に最も重要なのは、有機JASマークの確認です。
このマークは、農薬や化学肥料を使用せずに栽培されたことを示す日本の認証マーク。
パッケージに表示されているか、しっかり確認しましょう。
表示がない場合は、製造元に問い合わせて確認するのも良いでしょう。
安心してオーガニックティーを飲むためには、このマークの存在が大きな安心材料となります。
茶葉の種類と特徴
オーガニックティーは、紅茶、緑茶、ハーブティーなど、実に様々な種類があります。
紅茶は、アッサムやダージリンなど、産地によって風味や香りが大きく異なります。
緑茶は、煎茶や抹茶など、製法によって異なる味わいを持ちます。
ハーブティーは、カモミールやペパーミントなど、ハーブの種類によってリラックス効果や健康効果も様々です。
それぞれの茶葉の特徴を理解し、自分の好みに合ったものを選ぶことが大切です。
例えば、リラックスしたいならカモミールティー、スッキリしたいならペパーミントティーなどがおすすめです。
産地と栽培方法の確認
茶葉の産地や栽培方法も、オーガニックティーを選ぶ上で重要なポイントです。
同じ種類のお茶でも、産地によって風味や香りが異なり、栽培方法によって品質にも影響します。
パッケージに記載されている産地や栽培方法の情報を確認し、納得できるものを選びましょう。
例えば、標高の高い場所で育った茶葉は、独特の風味を持つ場合があります。
また、有機栽培されているかどうかだけでなく、フェアトレード認証を受けているかどうかも確認すると、生産者への配慮も考慮できます。
信頼できるブランドの選択
オーガニックティーを選ぶ際には、信頼できるブランドを選ぶことも大切です。
長年オーガニックティーの生産に携わってきたブランドは、品質管理がしっかりしており、安心して飲むことができます。
口コミやレビューを参考に、自分に合ったブランドを見つけるのも良いでしょう。
また、ブランドの理念や取り組みなどを確認し、自身の価値観と合致するブランドを選ぶことも重要です。
信頼できるブランドを選ぶことで、より安心安全なオーガニックティーを手に入れることができます。

オーガニックティーの健康効果
リラックス効果と成分
オーガニックティーには、多くの種類にリラックス効果があります。
カモミールティーやラベンダーティーなどは、特にリラックス効果が高いとされています。
これらの効果は、茶葉に含まれる様々な成分によるものです。
例えば、カモミールティーに含まれるアピゲニンという成分には、鎮静作用があると言われています。
リラックス効果を得るためには、寝る前に一杯飲むのがおすすめです。
ただし、効果には個人差がありますので、自分に合った飲み方を試行錯誤することが重要です。
美容効果と抗酸化作用
多くのオーガニックティーには、美容効果が期待できます。
特に、緑茶や紅茶に含まれるカテキンやポリフェノールには、強い抗酸化作用があり、老化の原因となる活性酸素の働きを抑える効果が期待されています。
また、ルイボスティーに含まれるSOD酵素も、抗酸化作用が高いことで知られています。
これらの成分を摂取することで、肌の老化を防ぎ、美肌を保つ効果が期待できます。
毎日の習慣として継続的に摂取することで、より効果を実感できるでしょう。
健康維持への貢献
オーガニックティーは、健康維持にも貢献します。
緑茶や紅茶に含まれるカテキンには、免疫力を高める効果があるとされています。
また、ハーブティーの中には、消化促進効果や風邪予防効果があるものもあります。
オーガニックティーを毎日の生活に取り入れることで、健康的な生活を送る一助となるでしょう。
ただし、健康効果は、あくまで補助的なものであり、病気の治療を目的としたものではないことを理解しておきましょう。
摂取方法と注意点
オーガニックティーの摂取方法は、種類によって異なります。
一般的には、熱湯を注いで数分間蒸らす方法が一般的です。
ただし、ハーブティーの中には、煮出す必要があるものもあります。
パッケージに記載されている使用方法を必ず確認し、正しく摂取しましょう。
また、飲みすぎると、胃腸の不調をきたす可能性もあるため、適量を心がけることが大切です。
妊娠中や授乳中の方、持病のある方は、医師に相談してから飲むようにしましょう。

まとめ
オーガニックティーは、健康志向の高い消費者の間で人気が高まっており、その選び方と健康効果への関心は高いです。
有機JASマークの確認、茶葉の種類や特徴、産地と栽培方法、信頼できるブランドの選択が、適切なオーガニックティー選びの鍵となります。
リラックス効果、美容効果、健康維持への貢献など、オーガニックティーは様々な健康効果をもたらす可能性を秘めています。
しかし、摂取方法や注意点を守り、自分に合ったオーガニックティーを適量楽しむことが重要です。
毎日のティータイムを、より健康で豊かな時間にしていきましょう。
-
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2023-09
- 2022-12
- 2022-05
- 2021-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2016-04
- 2013-03
- 2013-01
- 2012-10
- 2012-08
- 2012-05
- 2012-04
- 2012-03
- 2012-02
- 2011-12
- 2011-10
- 2011-09
- 2011-04