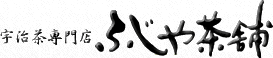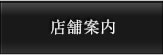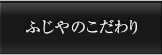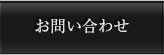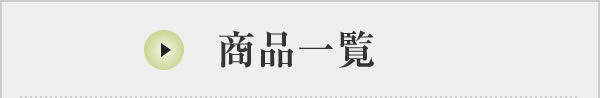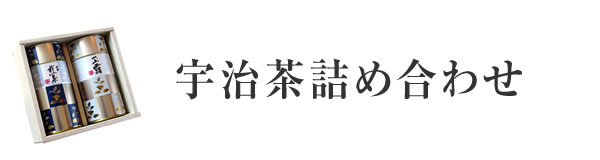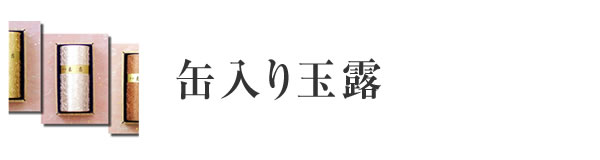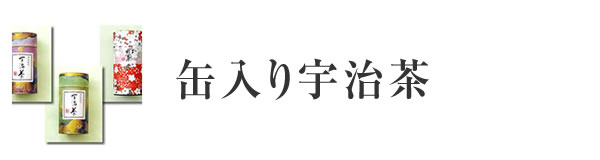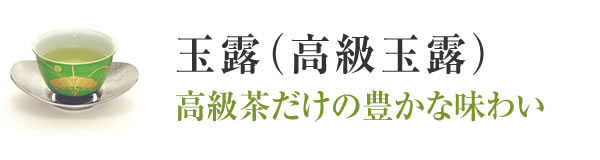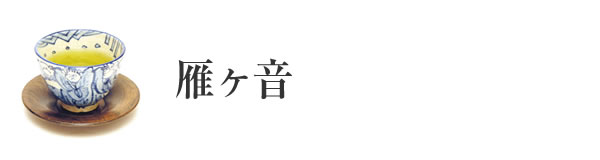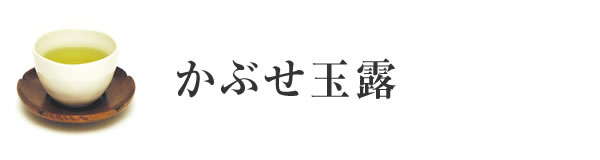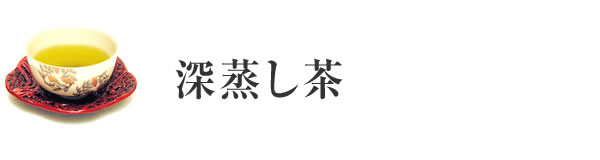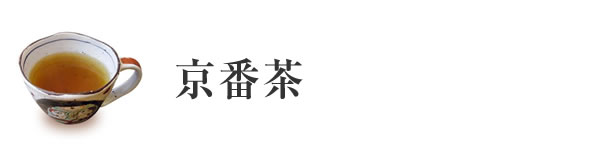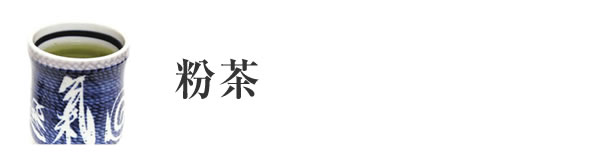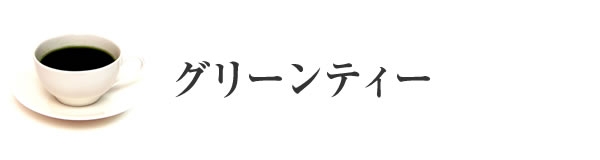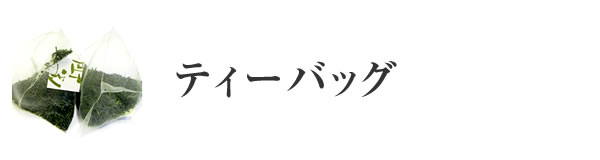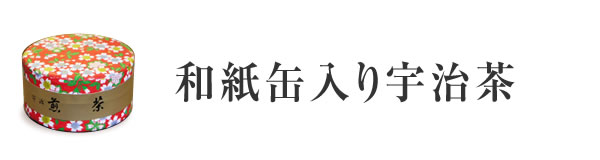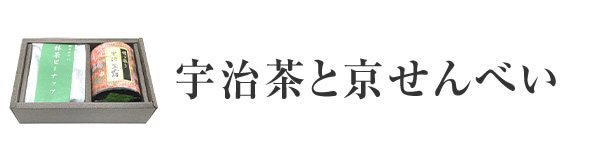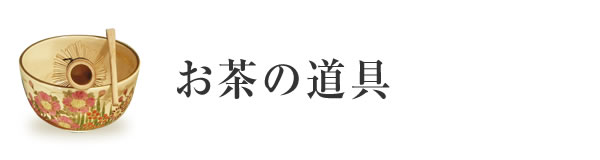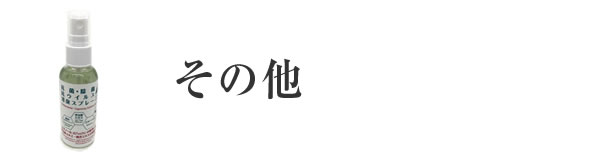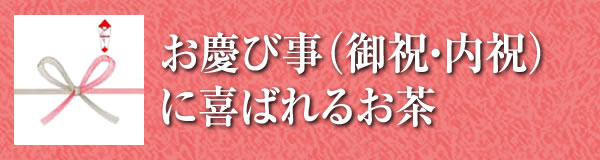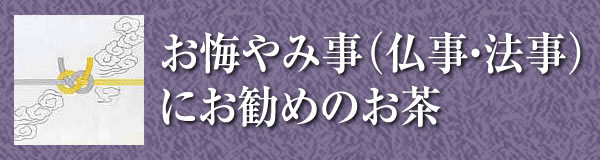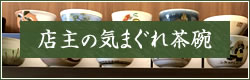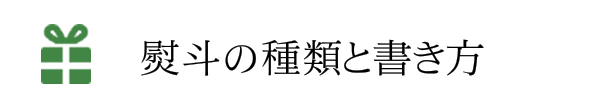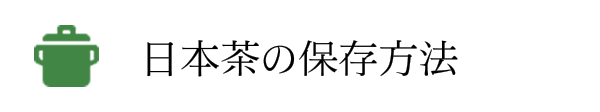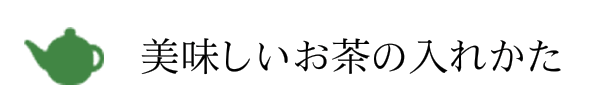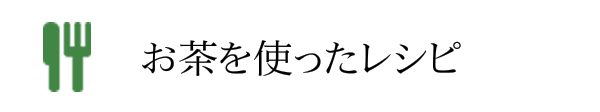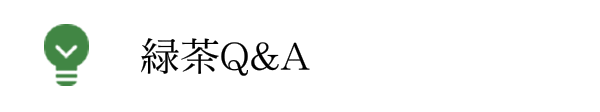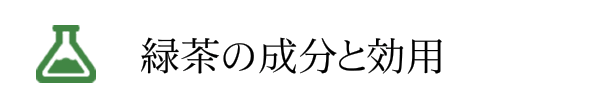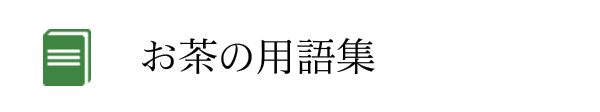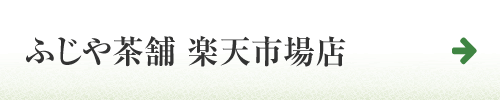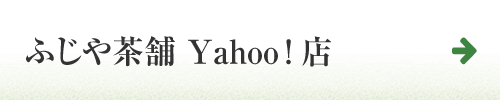- 2025-08-19 (火) 6:00
- お役立ちコラム

大切な故人の冥福を祈る法要。
僧侶への感謝の気持ちを表すためのおもてなしは、故人への供養にもつながります。
しかし、お坊さんにお菓子やお茶を出す際の適切なマナーは、意外と知られていないものです。
慌ただしい法事の準備の中で、失礼のないようにしたいと願う方も多いのではないでしょうか。
今回は、お坊さんへの心遣いが伝わる、お茶菓子の選び方と、お茶の入れ方に関するマナーをご紹介します。
お坊さんに出すお菓子を選ぶポイント
法事の状況に合わせたお菓子選び
法事では、僧侶への訪問は読経や弔いの儀式を行うためです。
そのため、お菓子は「その場で食べられるもの」と「持ち帰れるもの」の両方を考慮して選びましょう。
読経後、すぐに次の法事に向かう僧侶もいるため、個包装で日持ちするものが好ましいです。
一口、二口で食べられる大きさのものが、会話の妨げにならずおすすめです。
和菓子では饅頭や最中、洋菓子ではクッキーやマドレーヌなどが適しています。
スナック菓子のようなものは避けましょう。
好みに配慮したお菓子のセレクト
お坊さんの好みを知ることは難しいですが、事前に故人のご家族や関係者から情報を得たり、さりげなく尋ねたりするのも一つの方法です。例えば、「甘いものがお好きかどうか」を尋ねることで、より好まれるお菓子を選ぶことができます。
複数種類用意し、好みが分からなければ、和菓子と洋菓子の両方を用意するのも良いでしょう。
地域差のあるマナーへの対応
お茶菓子のマナーは地域差がある場合があります。不安な場合は、事前にご家族や近隣の方々に相談し、地域の慣習に沿った対応をすることをお勧めします。
地域によっては、特定の種類のお菓子が好まれる場合もあります。

お茶の入れ方とマナー
お坊さんへの適切なタイミング
お茶とお菓子を出すタイミングは、主に僧侶の到着時と読経後(法話後)の2回です。読経時間が長い場合は、休憩時にもお茶を出すと喜ばれるでしょう。
到着時は、お茶だけでも構いません。
しかし、読経後は、お茶とお菓子の両方をお出しするのが一般的です。
お茶の種類と入れ方
お茶の種類に決まりはありません。日本茶、ほうじ茶、麦茶など、好みに合わせて選んで構いません。
ペットボトルのお茶でも失礼にはあたりません。
ただし、温度には配慮が必要です。
夏場は冷たいお茶が好まれる場合が多いですが、温かいお茶を好む僧侶もいるため、状況に応じて、常温のお茶も用意しておくと安心です。
また、お茶の温度は、玉露50~60度、煎茶70~80度、番茶やほうじ茶は100度が目安です。
丁寧なもてなしのための準備
お茶とお菓子は、清潔な容器や器に盛り付けましょう。個包装のお菓子はそのままお皿に、個包装でない場合は懐紙を敷いてから飾り付けます。
懐紙の折り方は、弔事用(左下がり)を心がけてください。
お茶碗とお茶托は、僧侶を優先して用意し、参列者より格の高いものを使いましょう。
おしぼりもお忘れなく。
お盆を使用し、お茶碗とお茶托は別々に運び、お茶を注いでから提供するのが基本です。

まとめ
お坊さんへの心遣いは、法要を円滑に進めるだけでなく、故人への供養にも繋がります。お菓子は個包装で持ち帰りやすく、一口サイズで食べやすいものを選びましょう。
お茶は、到着時と読経後(法話後)の2回、状況に応じて休憩時にも提供しましょう。
お茶の種類や温度、お菓子の種類は、地域差や僧侶の好みに合わせて柔軟に対応することが大切です。
丁寧な準備と心遣いを忘れず、故人への感謝の気持ちを表しましょう。