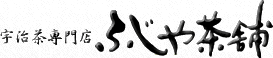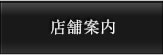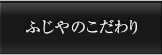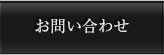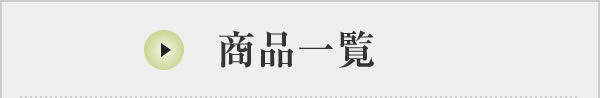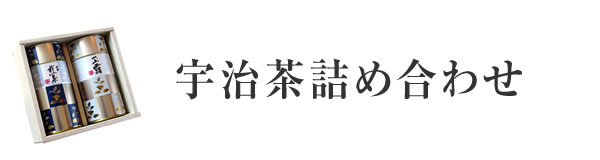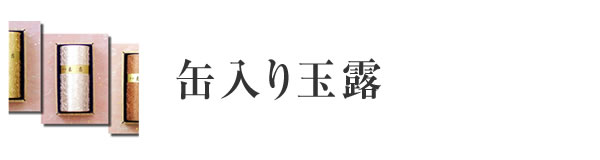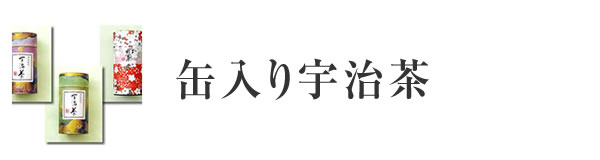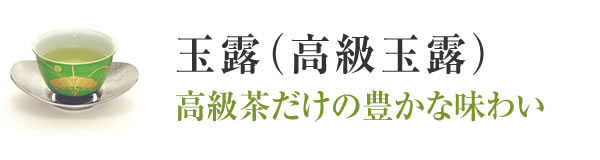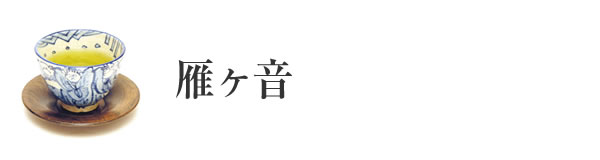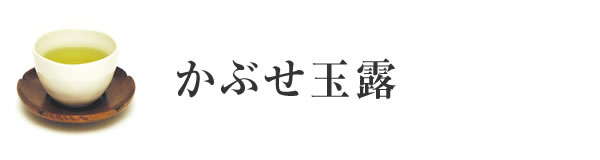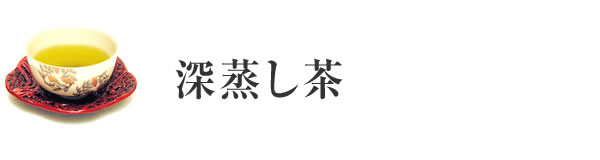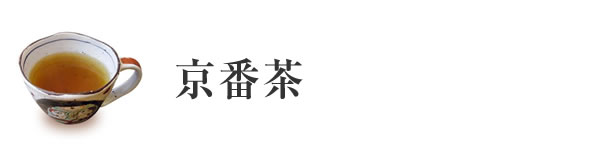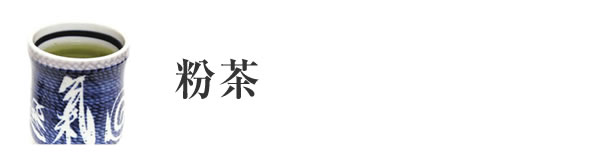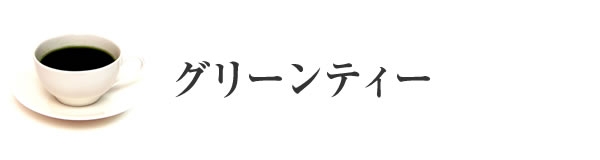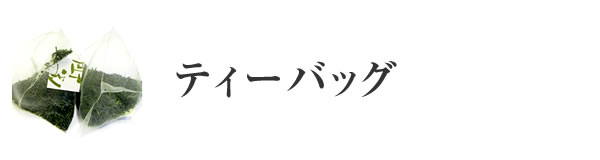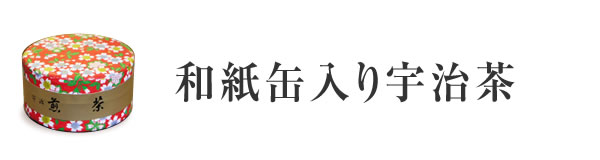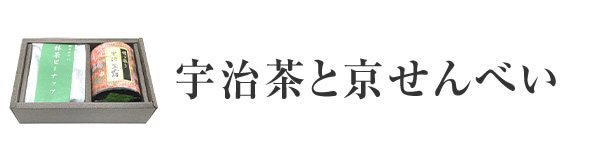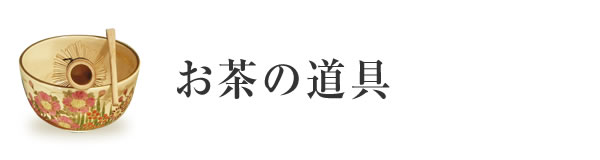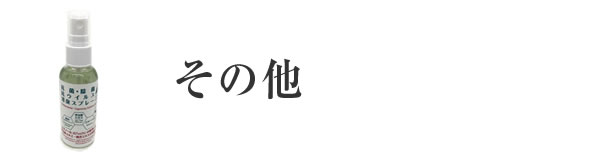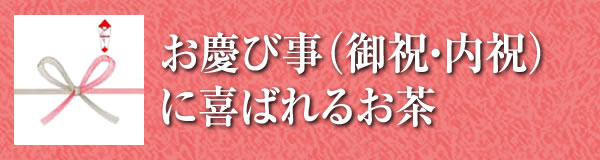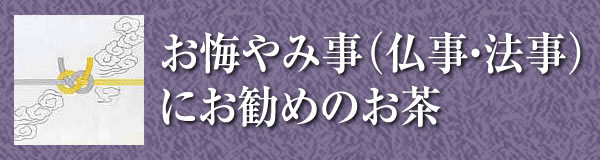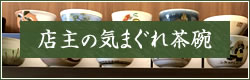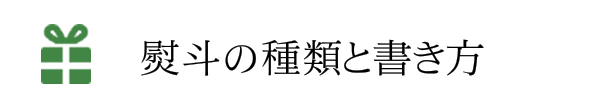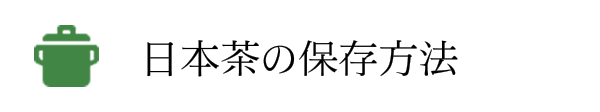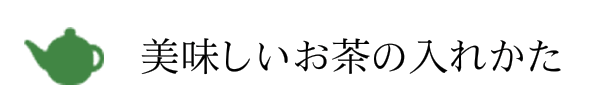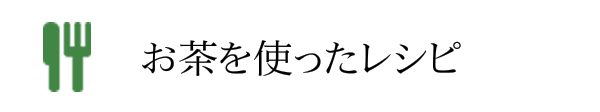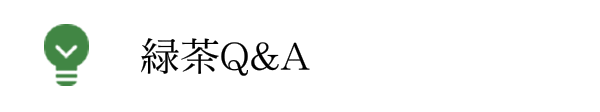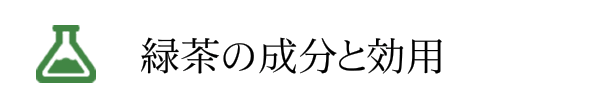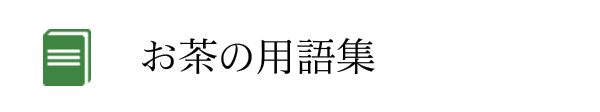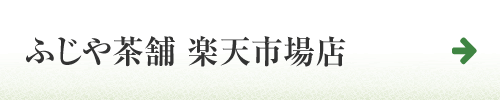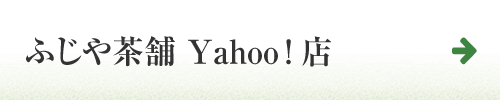- 2025-10-10 (金) 6:00
- お役立ちコラム
これらの飲み物に共通する成分として「タンニン」が挙げられます。
タンニンは、私たちが普段口にする様々な食品や飲料に含まれる成分です。
しかし、その含有量や人体への影響については、まだ十分に理解されていない部分も多いといえます。
今回は、タンニンの定義や種類、性質、そして様々な食品や飲料における含有量について解説します。
タンニンとは
タンニンの定義
タンニンとは、植物に含まれるポリフェノールの一種で、渋みをもたらす成分です。
分子構造は複雑で様々な種類があり、その構造によって性質や生理作用も異なります。
また、水溶性で、タンパク質やアルカロイドと結合しやすい性質を持っています。
この性質から、皮なめしやインクの製造にも利用されてきました。
さらに、近年ではタンニンの持つ様々な生理活性についても研究が進められています。
タンニンの種類と構造
タンニンは、加水分解性タンニンと縮合性タンニンに大別されます。
加水分解性タンニンは、酸や酵素によって加水分解され、より小さな分子に分解されます。
一方、縮合性タンニンは、複雑な縮合構造を持ち、加水分解されにくい性質を持っています。
それぞれの構造の違いによって、渋みの強さや生理活性も異なり、食品や飲料への影響も様々です。
例えば、加水分解性タンニンは渋みが強い一方、縮合性タンニンは渋みが穏やかな傾向があります。
また、構造の複雑さから、様々な種類があり、その特定や含有量の正確な測定には高度な分析技術が必要になります。
タンニンの性質
タンニンは、水に溶ける性質を持ち、独特の渋みを与えます。
また、タンパク質と結合する性質を持つため、タンパク質の凝固作用を示します。
この性質を利用して、皮なめしやインクの製造などに用いられてきました。
さらに、抗酸化作用や抗菌作用なども有することが知られており、健康への影響も注目されています。
例えば、抗酸化作用は老化防止に役立つと考えられており、抗菌作用は食中毒予防に効果的である可能性があります。
食品・飲料別のタンニン含有量一覧
紅茶のタンニン含有量
紅茶のタンニン含有量は、茶葉の種類や製法、抽出時間などによって大きく変動します。
一般的に、アッサム紅茶やダージリン紅茶などの茶葉では、乾燥重量に対して5~20%程度のタンニンが含まれているとされています。
抽出時間の長さによっても含有量は変化し、長時間抽出すると含有量が増加します。
そのため、紅茶のタンニン含有量を調整するには、茶葉の種類や抽出時間などを考慮する必要があります。
コーヒーのタンニン含有量
コーヒー豆の種類や焙煎度合いによって含有量は異なります。
一般的にコーヒー豆には、乾燥重量に対して3~8%程度のタンニンが含まれていると言われています。
抽出方法によっても含有量は変化します。
フレンチプレスなど長時間抽出する方法は、ドリップ式よりも含有量が多くなります。
また、焙煎が深いほどタンニンは減少する傾向があります。
ワインのタンニン含有量
ワインのタンニン含有量は、ブドウの種類や栽培方法、醸造方法などによって大きく異なります。
赤ワインは、ブドウの皮や種子からタンニンが抽出されるため、白ワインよりも含有量が多い傾向があります。
一般的に、赤ワインでは、1リットルあたり数グラムから数十グラムのタンニンが含まれているとされています。
そのため、赤ワインの渋みはタンニンに由来するものが多いのです。
緑茶のタンニン含有量
緑茶のタンニン含有量は、茶葉の種類や製法によって異なります。
一般的に、乾燥重量に対して10~30%程度のタンニンが含まれているとされています。
煎茶や玉露など、高品質の緑茶は特に含有量が多い傾向があります。
また、抽出時間や温度によっても影響を受け、高温で長時間抽出すると含有量が増加します。
さらに、二煎目、三煎目と抽出を繰り返すとタンニン含有量は減少していきます。
タンニン含有量の多い食品・飲料は?
タンニンを多く含む食品
タンニンを多く含む食品としては、渋柿、ブルーベリー、ザクロ、イチゴ、ブドウの皮などがあります。
これらの食品は、渋みが特徴的な味わいを持ちます。
また、ナッツ類や大豆製品にも、一定量のタンニンが含まれています。
これらの食品は、私たちの食生活において日常的に摂取されているものであり、タンニンの摂取に大きく貢献しているといえます。
さらに、ココアやチョコレートにもタンニンが含まれています。
タンニンを多く含む飲料
タンニンを多く含む飲料としては、紅茶、コーヒー、ワイン、緑茶などが挙げられます。
これらの飲料は、世界中で広く愛飲されており、多くの人々が日常的に摂取しています。
特に、濃いめに抽出された紅茶やコーヒー、フルボディの赤ワインなどは、タンニン含有量が高くなる傾向があります。
また、カカオ豆から作られるココアやチョコレートドリンクにもタンニンが含まれています。
含有量の多い食品・飲料の摂取時の注意点
タンニンを多く含む食品や飲料を大量に摂取すると、消化不良や便秘、鉄分の吸収阻害といった症状を引き起こす可能性があります。
特に、鉄欠乏症の人は、注意が必要です。
また、タンニンには、薬物との相互作用の可能性もあるため、薬を服用している人は、摂取量に注意しましょう。
過剰摂取にならないよう、バランスの良い食生活を心がけることが大切です。
タンニンを多く含む食品・飲料のメリット・デメリット
タンニン摂取のメリット
タンニンには、抗酸化作用、抗菌作用、抗ウイルス作用など、様々な生理活性が報告されています。
抗酸化作用によって、活性酸素による細胞へのダメージを防ぎ、老化防止や生活習慣病予防に効果があると考えられています。
また、抗菌作用や抗ウイルス作用によって、感染症予防にも貢献する可能性があります。
さらに、一部の研究では、タンニンに抗がん作用や血糖値上昇抑制効果があることも示唆されています。
タンニン摂取のデメリット
タンニンを過剰摂取すると、消化不良や便秘、鉄分の吸収阻害などの症状が現れる可能性があります。
特に、鉄欠乏症の人は、注意が必要です。
また、タンニンは、一部の薬物と相互作用を起こす可能性があるため、薬を服用している人は、摂取量に注意する必要があります。
さらに、タンニンは、口の中の粘膜に結合して収れん作用を示すため、過剰摂取により口の中の乾燥や渋みを感じることがあります。
タンニン摂取における注意点
タンニンは、体に良い効果をもたらす一方で、過剰摂取によるデメリットも存在します。
そのため、バランスの良い食事を心がけ、過剰摂取にならないように注意することが大切です。
妊娠中や授乳中の人、病気療養中の人などは、特に注意が必要です。
医師や専門家への相談も考慮しましょう。
適度な摂取を心がけることで、タンニンの健康効果を享受できるでしょう。
タンニン含有量の測定方法
タンニン含有量の測定方法
タンニン含有量の測定には、様々な分析方法があります。
例えば、フォールインデックス法や分光光度法などが用いられます。
これらの方法は、専門的な知識や機器が必要となるため、一般の人が行うのは困難です。
正確な含有量を測定するには、専門機関に依頼することが必要でしょう。
また、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いた分析方法も近年普及してきています。
家庭でできる簡易的な測定方法
家庭でタンニン含有量を正確に測定することは困難です。
しかし、お茶の色や渋みなどを目安に、大まかな含有量を推測することは可能です。
例えば、紅茶を抽出する際に、茶葉の量や抽出時間などを変えることによって、色の濃さや渋みの強さを比較することができます。
ただし、この方法はあくまで目安であり、正確な測定値ではありません。
あくまで、相対的な比較に留めておく方が良いでしょう。
まとめ
タンニンは植物由来のポリフェノールで、紅茶やコーヒー、ワインなどの渋みを生む成分として知られています。
抗酸化作用や抗菌作用など健康への有益な効果が期待される一方で、過剰摂取は消化不良や鉄分吸収阻害を引き起こす可能性があります。
食品や飲料ごとに含有量は大きく異なるため、適度な摂取を心がけることが大切です。
バランスよく取り入れることで、タンニンの持つ魅力を安全に楽しむことができるでしょう。