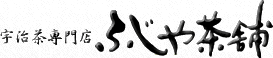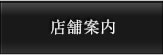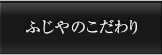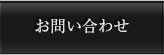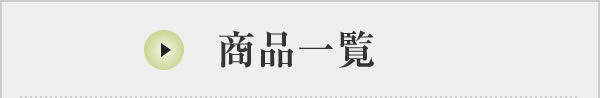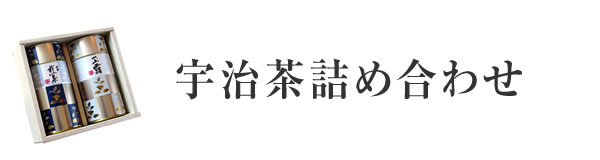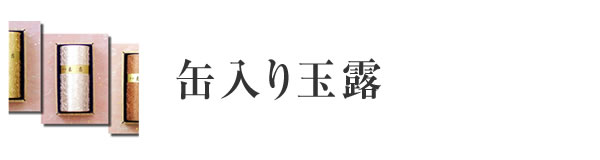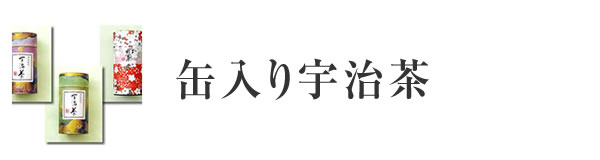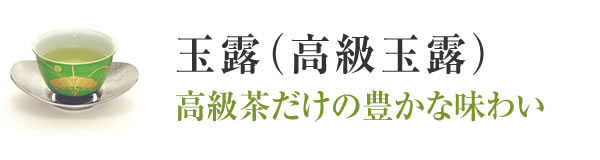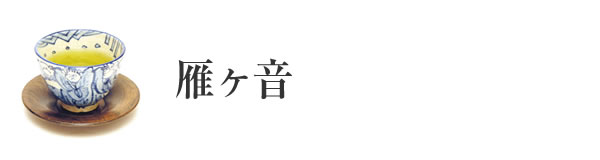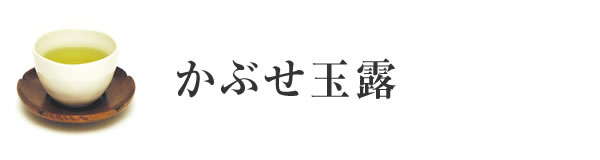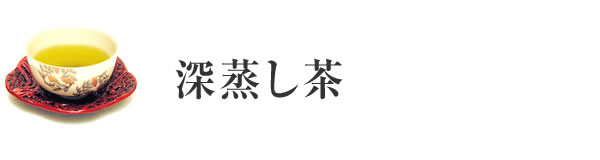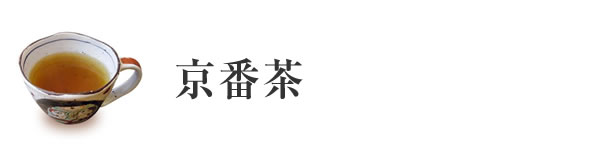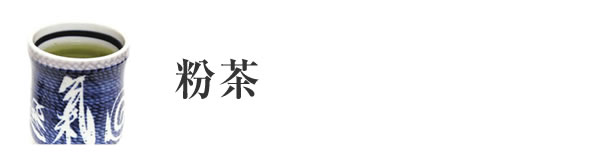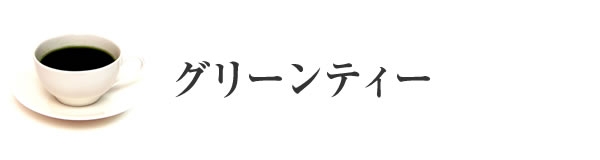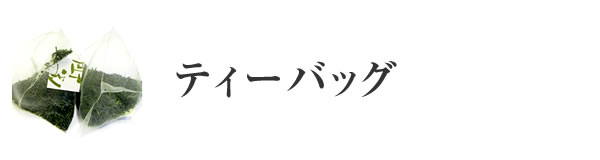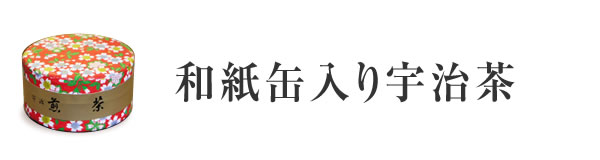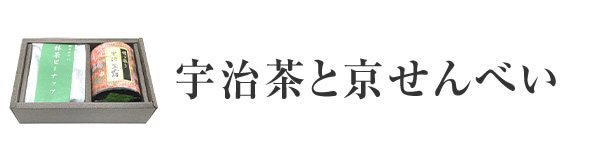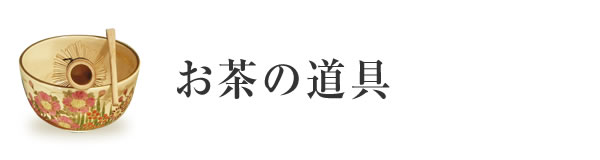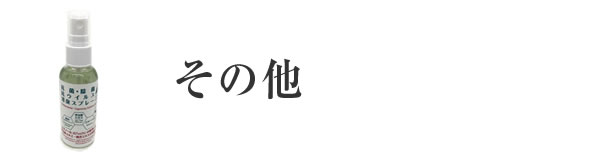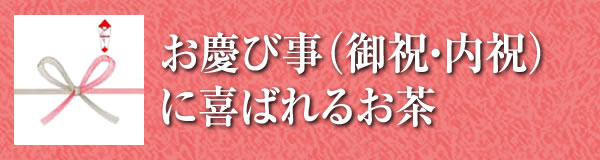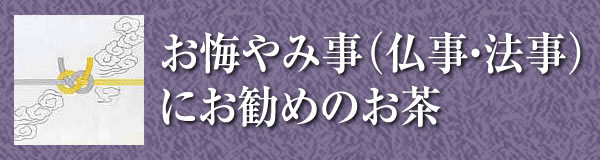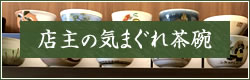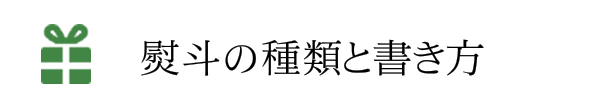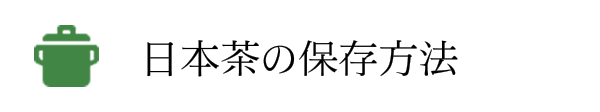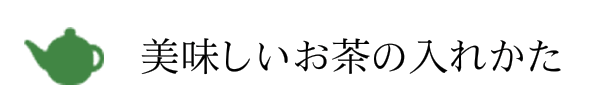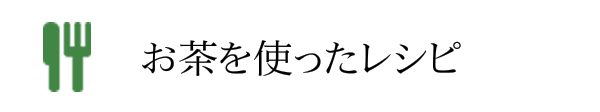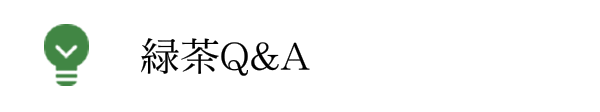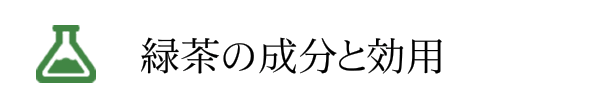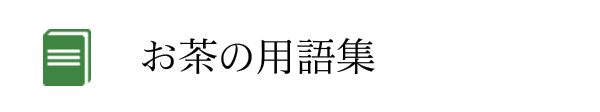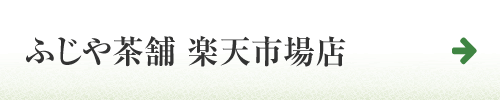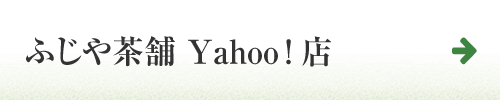2025-06
ほうじ茶・時間がたつとどうなる?香りと味・保存方法を解説
- 2025-06-03 (火)
- お役立ちコラム

ほうじ茶の香ばしい風味、あなたはどんなふうに感じていますか。
熱いお茶でいただくのはもちろん、冷たく冷やして飲むのもまた格別です。
しかし、淹れたての風味と、時間が経った後の風味は、どのように変化していくのでしょうか。
実は、その変化には明確な理由があり、最適な飲み頃や保存方法も存在します。
この記事では、ほうじ茶の時間の経過による風味の変化を、科学的な側面も交えながら詳しくご紹介します。
最後まで読んでいただければ、より一層ほうじ茶の魅力を堪能できるようになるでしょう。
ほうじ茶が時間経過で変化する理由
香りの変化とメカニズム
ほうじ茶の香りは、焙煎によって生まれる成分によるものです。
時間の経過とともに、これらの揮発性の高い成分は空気中に放散され、香りが弱まっていく傾向があります。
特に、強い焙煎香は比較的早く失われます。
そのため、淹れたての香ばしい香りを存分に楽しむには、早めに飲むことが重要です。
味の変化とメカニズム
香りの変化と同様に、味の変化も成分の揮発や酸化が原因です。
焙煎によって生まれた独特の甘みやコクは、時間が経つと徐々に薄れていきます。
また、お茶に含まれるタンニンは、空気に触れることで酸化し、渋みが強くなる可能性があります。
一方、水出しの場合、タンニンやカフェインの抽出量が少なくなるため、渋みが少なく、まろやかな風味を長く楽しめる傾向があります。
成分の変化とメカニズム
ほうじ茶の主要な成分であるカフェインやタンニンは、時間経過とともに変化します。
特に、高温で抽出されたお茶では、カフェインの溶出量が多くなりますが、時間が経つと酸化が進み、その量は減少していくと考えられます。
タンニンも同様に、時間の経過とともに変化し、渋みが変化したり、香りが変化する原因となる可能性があります。
水出しの場合、これらの成分の抽出量は少なく、変化も緩やかです。

ほうじ茶の最適な飲み頃と保存方法
時間による風味の変化
ほうじ茶は、淹れたての香りが最も強く、甘みとコクも感じられます。
時間が経つと、香りは弱まり、味がまろやかになっていきます。
しかし、保存状態によっては、渋みが増したり、酸化による風味の劣化も起こる可能性があります。
そのため、最適な飲み頃は、その日のうちに飲むのが理想的です。
水出しの場合は、冷蔵庫で保存すれば、より長く風味を保てます。
保存方法と賞味期限
ほうじ茶は、空気に触れると酸化が進むため、密閉容器に入れて、冷暗所に保存するのがおすすめです。
また、高温多湿の場所を避け、直射日光も避けるべきです。
賞味期限は商品によって異なりますが、開封後はなるべく早めに飲み切るようにしましょう。
特に、水出しの場合は、冷蔵庫で保存し、1日以内に飲み切るのが理想的です。
茶葉の状態にもよりますが、適切な保存をすれば、数日間は風味を維持できる可能性があります。
おいしく飲むためのコツ
ほうじ茶をより美味しく楽しむために、茶葉の量や抽出時間、水温などを調整してみましょう。
また、茶器の種類によっても風味は変化します。
自分にとって最適な方法を見つけることが、より豊かなお茶の時間を生み出します。
季節や気分に合わせて、様々な飲み方を楽しむのもおすすめです。
例えば、暑い日は水出しほうじ茶を、寒い日は熱々のお湯で淹れたほうじ茶を、と使い分けるのも良いでしょう。

まとめ
この記事では、ほうじ茶の時間の経過による風味の変化と、最適な飲み頃、そして保存方法について解説しました。ほうじ茶の香りは揮発性が高いため、淹れたての香りが一番です。
しかし、時間経過による風味の変化もまた、ほうじ茶の奥深さと言えるでしょう。
適切な保存方法と飲み頃を理解することで、より一層、ほうじ茶の豊かな風味を堪能できるはずです。
ぜひ、今日からのお茶の時間に役立ててみてください。
様々な淹れ方や保存方法を試して、あなたにとって最高のほうじ茶の楽しみ方を見つけてください。
ほうじ茶の殺菌効果・そのメカニズムと日常生活への応用
- 2025-06-01 (日)
- お役立ちコラム
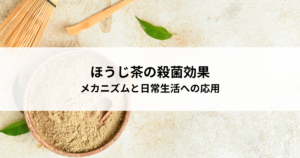
ほうじ茶、その香ばしい香りと深い味わいは、多くの人を魅了します。
古くから親しまれてきたこのお茶には、リラックス効果や抗酸化作用といった様々な効能が知られていますが、実は「殺菌効果」も注目されているのです。
日常的に飲むお茶が、私たちの健康を様々な面から支えてくれるとしたら、とても興味深いと思いませんか。
この記事では、ほうじ茶の殺菌効果に焦点を当て、そのメカニズムや具体的な応用について探っていきましょう。
普段何気なく飲んでいるほうじ茶の意外な一面を発見できるかもしれません。
ほうじ茶の殺菌メカニズム
カテキン類の抗菌作用
ほうじ茶に含まれるカテキン類は、強力な抗菌作用を持つポリフェノールの一種です。
その中でも、エピガロカテキンガレート(EGCG)は特に高い抗酸化力と抗菌力を持ち、様々な菌の増殖を抑制する効果が期待できます。
具体的には、細菌の細胞膜を破壊したり、酵素の働きを阻害することで、菌の増殖を阻止します。
殺菌効果の科学的根拠
多くの研究で、ほうじ茶のカテキン類が、様々な細菌やウイルスに対して抗菌作用を示すことが確認されています。
例えば、食中毒の原因菌であるO-157や、虫歯の原因菌であるミュータンス菌などへの効果が報告されています。
これらの研究結果から、ほうじ茶の殺菌効果は科学的に裏付けられていると言えるでしょう。
メカニズムの解明
カテキン類の抗菌メカニズムは、まだ完全に解明されているわけではありません。
しかし、現在までに、細菌細胞膜への作用、酵素活性阻害、遺伝子発現への影響など、複数のメカニズムが関与していると考えられています。
今後の研究によって、より詳細なメカニズムが明らかになることが期待されます。

ほうじ茶殺菌効果の応用
日常生活での活用法
ほうじ茶の殺菌効果は、日常生活でも活用できます。
うがい薬として利用したり、口内環境の改善に役立てたりすることが可能です。
また、ほうじ茶の成分が、口臭の原因となる菌の増殖を抑える効果もあることから、口臭予防にも効果が期待できます。
食品保存への応用
ほうじ茶の抽出液を食品に添加することで、食品の腐敗を防ぐ効果が期待できます。
特に、傷みやすい生鮮食品の保存に活用する研究も進められています。
ただし、食品の種類や保存方法によっては、効果が異なる可能性があるため、適切な使用方法を検討する必要があります。
健康増進への効果
ほうじ茶を継続的に摂取することで、様々な感染症の予防に繋がる可能性があります。
特に、免疫力の低下しやすい高齢者や、病気療養中の方にとって、ほうじ茶は有用な飲み物と言えるかもしれません。
ただし、ほうじ茶だけで全ての感染症を予防できるわけではありません。
バランスの良い食事や適切な運動も併せて行うことが大切です。

まとめ
この記事では、ほうじ茶の殺菌効果について、そのメカニズム、具体的な応用、そして健康増進への効果について解説しました。ほうじ茶に含まれるカテキン類の抗菌作用は、科学的に裏付けられたものであり、日常生活や食品保存、健康増進など、様々な場面で活用できる可能性を秘めています。
もちろん、万能薬ではありませんが、健康維持の一助として、ぜひ日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
芳醇な香りと共に、健康的な毎日を送るための一杯を、楽しんでください。
-
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2023-09
- 2022-12
- 2022-05
- 2021-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2016-04
- 2013-03
- 2013-01
- 2012-10
- 2012-08
- 2012-05
- 2012-04
- 2012-03
- 2012-02
- 2011-12
- 2011-10
- 2011-09
- 2011-04